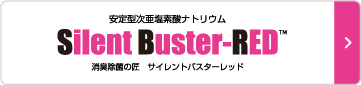〜時代を映すモノと、残された人へのメッセージ〜
遺品整理の現場には、ただの物ではなく「時代そのもの」が眠っています。
古い冷蔵庫、使い込まれた急須、色あせた写真――それらは、使われていた頃の暮らしや空気感をそのまま閉じ込めています。
同じ“テレビ”でも、昭和40年代のブラウン管と平成・令和の薄型テレビでは、形も重さも、そして役割も違います。
私たちは、そういったモノを通して「その時代の暮らし」を垣間見ることができます。
現場でよく見かけるのは、丸みを帯びた冷蔵庫や木目調のテレビ。
昭和40〜50年代には、家電はただの道具ではなく“ステータス”でもありました。
テレビは居間の主役、電話は家族の社交窓口。
黒電話を見つけると、家中に響く「ジリリリ!」の音や、家族で一台を順番に使ったその頃の光景が浮かびます。
平成に入ると、暮らしはぐっと軽やかになっていきます。
ビデオデッキやミニコンポ、ゲーム機など、“家族全員で使うもの”から“個人の趣味に特化した道具”が増えました。
遺品整理でゲームソフトやカセットテープが大量に出てくると、その方の趣味の世界が垣間見えます。
モノは時代を映すだけではなく、家族の歴史も語ります。
例えば、古い弁当箱や子どもの作品、手書きのレシピ帳や日々の出来事を記した手帳。
現場で見つけたレシピ帳には、味噌汁や煮物の分量が細かく書かれており、手帳のある1ページの隅には「今日は孫が来る」といった走り書きが。
そこには、日々の暮らしと家族を思う気持ちが込められていました。
時代が変わっても変わらないもの。
家電や家具の形は変わっても、「大切な人を思う気持ち」や「日々を大切に生きる姿勢」は変わりません。
遺品整理は、ただ物を片付ける作業ではなく、その人が歩んだ時代と心を紐解く仕事なのです。
誰かの歩んだ足跡は、私たちにとっての“もう一つの人生”です。
その一つひとつに耳を傾けることこそ、遺品整理の本当の価値。
そして、その出会いは私たち自身の生き方をも豊かにしてくれるのです。